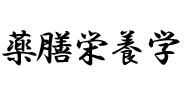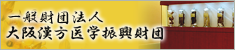季節の献立
秋
初秋と晩秋の二つのメニューです。
※分量は二人分で記載
初秋のメニュー(秋)
鯖のカレー塩麹焼
材料
- 鯖
- 160g
- 塩麹
- 大匙2
- カレー粉
- 小匙1/2
- レモン
- お好みで
- オリーブオイル
- 適量
作り方
1
鯖の切り身に塩麹とカレー粉をも見込み、2時間~一晩冷蔵庫で寝かせる。
2
鯖にオリーブオイルを軽く塗りあらかじめ3分ほど温めておいたグリルやオーブンで焼く。(両面焼きなら8分程度)
卵とトマトの彩り炒め
材料
- 卵
- 2個
- トマト
- 大1個
- 黄パプリカ
- 1個
- 椎茸
- 4本
- 三つ葉
- 半束
- オリーブオイル
- 大匙1
- バター
- 大匙1
- 塩
- 少々
- こしょう
- お好みで
作り方
1
トマトは、ヘタをくりぬき、熱湯にさっとくぐらせて、冷水にとり、皮をむく。
2
トマト、黄パプリカ、椎茸を大きめの乱切りにする。
3
フライパンを熱し、オリーブオイルを入れ、溶いた卵を流す。
4
卵はしばらくそっとしておき、底が固まってきたら大きく混ぜ全体に火が通ったらお皿にあげておく。
5
同じフライパンにオリーブオイルを足し、パプリカ、椎茸、トマトの順に炒めながら入れ、火を通す。
6
野菜に火が通ったら、塩少々と、バター、お好みでこしょうを入れ軽く混ぜ合わせる。
7
火を切って、フライパンに先ほどの焼いた卵と、切っておいた三つ葉を入れふんわり混ぜる。
8
味を見て、塩加減を調節する。
きゅうりとアボカドのわさび醤油和え
材料
- きゅうり
- 1本
- アボカド
- 1ケ
- 醤油
- お好みで
- わさび
- 少々
作り方
1
アボカドは皮をむいて種を取り、1.5センチの角切りにする。
2
きゅうりも同じように角切りにする。
3
わさび醤油で和える。
冬瓜のスープ
材料
- 鶏ミンチ
- 100g
- 冬瓜
- 150g
- 鶏ガラスープ(鰹出汁)
- 400㏄
- 白ネギ
- 1/3本
- 針生姜
- お好みで
- 酒
- 大匙1
- 醤油
- 小匙2
- 塩
- 小匙1/2
- 片栗粉
- 大匙1
作り方
1
冬瓜は、皮をむぎ、大きめの角切りにする
2
鶏ミンチに塩少々を振り、熱した鍋で炒める。
3
肉に火が通ったら、冬瓜を加え軽く炒める。
4
スープ、細切りにした白ネギを加えて煮込む。
5
酒、醤油、塩を加え、さらに煮込む。
6
具材に味が染みたら、針生姜を加え、水溶き片栗粉でとろみをつける。
レンコンのお焼き
材料
- 桜エビ
- 大匙1
- レンコン
- 200g
- 山芋
- 100g
- 片栗粉
- 50g
- ニラ
- 適量
- 青のり
- 適量
- 塩
- 少々
- 菜種油
- 適量
- 酢醤油
- お好みで
作り方
1
レンコンは粗みじん切りにする。ニラは小口切りにする。
2
山芋はすり鉢かフードプロセッサーですり潰す。
3
桜エビ、レンコン、山芋、片栗粉、ニラ、青のり、塩少々をボールで混ぜる。
4
熱したフライパンに菜種油を引き、生地を平たくて丸い形にし、両面をこんがり焼く。
5
お好みで酢醤油をかけていただく。
栄養価
- たんぱく質
- 59.6g
- 鉄
- 7.7㎎
- ビタミンB1
- 0.78㎎
- ビタミンB12
- 24.1㎎
- ビタミンC
- 120㎎
コメント
初秋の暑さと肌寒さが同居する季節にぴったりの献立です。
・鯖のカレー塩麹焼の魚はサンマの開き、鰆などで代用できます。
・冬瓜の余った分は、切って冷凍することができます。冷凍しておいてお味噌汁などに入れることもできます。
・スープに動物性のたんぱく質を加えることで、アミノ酸の栄養バランスがアップします。
・これだけしっかり食事をとっていても、ビタミン群の摂取量は意外と少なくなっています。サプリメントを利用することで体調の底上げをすることもできますが、食事をよく噛んで、たんぱく源や良質の脂質、根菜や海藻などをしっかり意識して摂ることで腸内環境を整え、胃腸の消化機能をあげることが大切です。
・米や小麦などの糖質を控え、根菜で糖質を摂ることで食物繊維やビタミンの摂取ができます。
薬膳コメント
初秋
鯖は性味は“平”で肺・腎の滋養になります。栄養学的にはきわめてEPA、DHAが豊富で、ビタミンB12、ビタミンDも含まれ抗酸化・抗加齢では注目の食材です。
カレーの辛味を使うことで、消化酵素が出やすくなり食欲増進、代謝活性すると共に軽度の発散効果もあるので食欲が低下しやすく熱がこもりやすい時期にとりいれてはいかがでしょう。カレーのマサラはすべて漢方薬です。
トマト・キュウリ・冬瓜は微寒または涼の食材です。まだ暑さがのこる時期にさっぱりとした食感で熱のこもりを去り、潤いを与えるのにふさわしいメニューです。
アボガドは森のバターと言われるように飽和脂肪酸を多く含みます。酸化しにくい安定したエネルギー源となり、ビタミンCやマグネシウムも含んでいます。
内臓の疲れを取りながらタンパク質や脂肪酸など、しっかりと栄養も摂取できます。
晩秋のメニュー(秋)
ししゃもの春巻き
材料
- 子持ちししゃも
- 6尾
- 海苔
- 3枚
- 大葉
- 6枚
- 春巻きの皮
- 3枚
- 水溶き小麦粉
- 適量
- レモン
- 適量
- 揚げ油(ラード)
- 適量
作り方
1
春巻きの皮は横長に半分に切る。
2
水溶き小麦粉をノリにして、大葉と海苔で巻いたししゃもを春巻きの皮で巻く。
3
180℃の油で揚げる。
4
お好みでレモンをかける。
ゆり根の卵とじ
材料
- 卵
- 3個
- しらす
- 20g
- ゆり根
- 60g
- 人参
- 60g
- しめじ
- 60g
- 三つ葉
- 20g
- 鰹だし
- 150㏄
- 醤油
- 小匙2
- みりん
- 小匙2
作り方
1
ゆり根は、キレイに洗い一枚ずつに分け、さっと洗う。
2
人参、しめじを食べやすい大きさに切りだし汁と調味料を入れ人参に火が通るまで煮る。
3
ゆり根を加えてさらに煮、ゆり根に火が通ったら溶いた卵としらすを入れ、卵とじにする。
4
火を消し、三つ葉を飾る。
ほうれん草のくるみ和え
材料
- ほうれん草
- 1束
- えのき
- 半束
- くるみ
- 30g
- 黒炒りゴマ
- 小匙1
- 醤油
- 小匙2
- みりん
- 小匙2
作り方
1
くるみは、フライパンで軽く炒ってすり鉢で粗目につぶす。
2
ほうれん草は、沸騰したお湯に塩をひとつまみ入れ、茹でて冷水にあげる。
3
えのきは食べやすい大きさに切ってさっと茹でる。
4
ほうれん草はしっかり水を絞り、食べやすい大きさに切る。
5
ほうれん草、えのき、くるみ、黒ごまをボールに入れ、混ぜる。
5
醤油とみりんで味付けをする。
サンラータン山椒風味
材料
- 豚切り落とし
- 80g
- 豆腐
- 1/3丁
- レタス
- 3枚
- 乾燥きくらげ
- 5g
- 干しシイタケ
- 2本
- 薄口醤油
- 大匙1
- 酢
- 大匙1
- ごま油
- 少々
- 山椒
- 少々
- 水(椎茸の戻し汁)
- 350㏄
作り方
1
干しシイタケは、前日から水につけて戻しておくか湯で戻す。
2
きくらげは水で戻す。
3
干しシイタケ、きくらげ、レタス、豆腐を食べやすい大きさに切る。
4
水と椎茸の戻し汁を半々くらいで混ぜ、醤油と酢をを加え火にかける。
5
干しシイタケときくらげを入れて5分ほど煮込む。
6
レタスと豆腐を加え、さっと火を通しごま油と、お好みで山椒を振りいただく。
栄養価
- たんぱく質
- 46.3g
- 鉄
- 6.3㎎
- ビタミンB1
- 0.63㎎
- ビタミンB12
- 9.6㎎
- ビタミンC
- 31㎎
コメント
寒さが目立ってきた晩秋向けのメニューです。
・ししゃもの春巻きは、お魚が苦手な方や子どもさんにも食べやすい料理です。また、頭からしっぽまで丸ごと食べられるので栄養バランスが良いです。
・魚卵は、栄養価が非常に高くミネラルやビタミンがたっぷり含まれています。
・ゆり根の卵とじは、ゆり根が手に入らなければ、じゃが芋や山芋などでも代用できます。
・卵とじの卵はいつもより多めに使うことで、たんぱく質の摂取量を増やします。
・酸味のあるスープは、いつもの汁物がマンネリ化したときに気分をかえるのにオススメです。
・くるみは、身体の材料にもなる良質の脂質がふくまれており、おやつなどにも良いです。
・身体の材料になり、食いだめのできないたんぱく源は、1回の食事で1種類だけではなく、肉・魚介類・大豆・卵のなかから2~3種類程度組み合わせ、しっかり摂取できるように意識しましょう。
薬膳コメント
初秋
ししゃもは性味では“平”で、寒熱に偏らず、この季節には使いやすい素材です。タンパク質、脂質の他に必要なビタミンB12、ビタミンD、Eやマグネシウム、カルシウム、亜鉛も比較的多く含まれまれ、養血や骨の老化に役立ちますし“陰の季節”(秋から冬)には大切な栄養素です。
海苔にはカルシウム、リン、鉄、マグネシウム、カリウム、ナトリウム、亜鉛、ヨウ素などが含まれます。漢方的には化痰作用といい、体液などから生じる余分な停滞を除くと言われています。
レモンや梅肉などのクエン酸は脂肪分解に役立ちます。
百合根は“潤肺”、“生津”という身体に必要な潤いを与えてくれる優秀な食品です。デンプン質が多いですが、タンパク質、ビタミンCを含んでいます。
くるみは薬膳的には性味は温で肺・腎を助け老化予防・便通にも良いとされています。オメガ3系の脂肪酸やビタミンEなども多く含んでおり、抗酸化に効果があります。
山椒は漢方薬でもあります。性味は辛・熱。消化器の手術後によく使われる大建中湯にも含まれており、腸を温めて蠕動運動を促進します。辛味は全身に受容体があり、身体が温まります。唾液やその他の消化酵素の分泌も刺激し、解毒や消化も助けます。